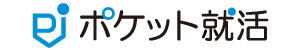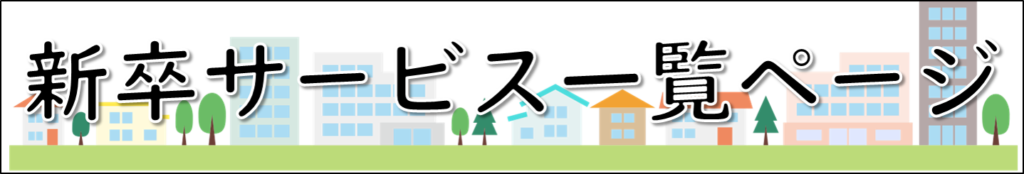学生時代のアルバイトは職歴とはなりませんが、アルバイトを通じて様々な経験や気づきも多いため、エントリーシートでのアピールは高評価につながる可能性もあります。しかし、
「アルバイト歴の記入欄にはどのようなことを書けばよいのかわからない」
「アルバイト歴を書く際、注意しなければいけないことはあるのだろうか?」
そんな疑問や不安をお持ちの就活生も多いことでしょう。
そもそも企業はどんな目的でアルバイト歴を質問するのでしょうか?
そこで当記事では、エントリーシートでのアルバイト歴の書き方やコツ、企業がチェックしているポイントなどを解説します。
エントリーシートのアルバイト歴、企業がチェックしているポイントとは?
社会経験があるのかどうか知りたいから
新卒採用者の中には、まだ学生気分が抜けず、責任感がないのでは?といった人もいます。
これでは企業側も仕事においてミスマッチを感じざるを得ないため、アルバイトとはいえ社会経験の有無を事前に知りたいため、エントリーシートを通じて質問します。
大半の企業で新入社員研修はありますが、働く上での責任や自覚は入社前から持っていることが大切になります。
自社の社風と合っているか知りたいから
学生にとってアルバイトは、好きな仕事や興味のある仕事から選ばれることが多く、そこから業界・企業選びの軸や価値観が見えることがあります。
この就活生はどのような仕事に魅力を感じ、そのアルバイトが自社の仕事に関連性はあるかなどを企業は確認しています。
例えば飲食店でのアルバイトと営業職では仕事内容は異なりますが、人に接してサービスを行うという点では共通です。
このように共通点や関連性があると、評価も高くなる可能性があります。
物事に取り組む姿勢を見たいから
アルバイトは労働の対価として、時給で報酬をもらっています。
学生がアルバイトを行う理由は様々ですが、多くは「お金稼ぎ」であり、生活費や自分の小遣いのためでしょう。
しかし、企業がエントリーシートを通じてアルバイト歴を質問する理由は、アルバイトを通じてどのように物事に取り組んできたのか、また、アルバイトを通じて何に気づき、学んだのかという点です。
何のアルバイトをしたのかより、そこから見える価値観や行動パターンが知りたいのです。
エントリーシートでアルバイト歴を書く際のポイント
会社や店舗の具体名は伏せる
エントリーシートでアルバイト歴を書く際、アルバイト先の企業名や店舗名を書く必要はなく、逆に書いてはいけないといった決まりもありません。
しかし、守秘義務や情報漏えいの観点から、また、アルバイト先が応募企業の競合先である可能性もあるため、会社名や店舗名は書かないことをおすすめします。
アルバイト歴を書く際は、「スーパーマーケットのレジ打ち」「飲食店の厨房」などのように、業務内容がわかるように書きましょう。
また、ファミリーレストランを「ファミレス」、コンビニエンスストアを「コンビニ」、アルバイトを「バイト」など略称で書くことは避けましょう。
アルバイトを通じて気づいたことや仕事に取り組む姿勢を盛り込む
前述のように、企業はエントリーシートのアルバイト歴欄から、その就活生がアルバイトを通じて何に気づき、どう学んだかという経験や価値観を知ろうとしています。
そのため、アルバイトから得られた成果や学びは、必ず書くようにしましょう。
一方、アルバイトであっても、仕事の上でぶつかる困難や問題もあります。そのとき、自分はそれを解決するためにどのように対処したかもアピールしましょう。
また、困難や問題に対処しきれず失敗もあるかもしれませんが、失敗したことを書くこと自体がマイナス評価にはなりません。仕事において、誰もが少なからずミスはします。
大切なのはその経験で得た気づきや学びなので、両面を伝えるとより強く人間性をアピールできるでしょう。
成果は具体的な数字で表わす
成果は漠然とした表現ではなく、できるだけ具体的な数字で表わすようにしましょう。
例えば「たくさんのお客様」や「売上アップに貢献」ではどれくらいの成果なのかがわからず採用担当者からの高評価にはつながらないでしょう。
人の場合は人数、売上なら額やパーセントで表し、その他の成果も時間や件数などの数値を用いると説得力も増します。
このように成果を数字で表わすことを「定量的」と呼びますが、どうしても数字で表わせない場合も「××だった状態を〇〇のように変えることができた」と「定性的」に表わすことがポイントになります。
明確なアピール事項を考える
「学生時代、〇〇のアルバイトで頑張りました」だけでは採用担当者の高評価にはつながりません。
前述のように、アルバイトを通じた気づきや学びを伝えることが重要ですが、さらにアルバイトで培ったスキルもあわせ、応募企業の仕事にどう活かすことができるかといったことにつなげましょう。
その際、どのようなことを企業にアピールすべきなのかを明確に考えることが大切になります。
イメージが悪いアルバイトもある
変わったアルバイト歴があると、個性のアピールにつながり、採用担当者の記憶に残ることもあります。
しかし、いくらインパクトがあるからといっても、違法で反社会的なアルバイトなどは論外です。
また、水商売などのアルバイトもイメージが悪くなってしまうことは十分理解しておきましょう。
アルバイト歴がない場合でも無記入は避ける
大学生の本業はあくまで勉学です。学部学科によっては課題が多く、アルバイトに時間が割けなかったという人もいるでしょう。
アルバイト経験がないということ自体、それがすぐにマイナス評価となるわけではありません。しかし、未経験であるにも関わらず、ウソをついて「経験あり」とすることは絶対にやめましょう。
アルバイト経験がない場合でも経歴欄を無記入にしたり、ただ「ありません」とだけ記入することはなんのアピールにもつながりません。
「ゼミで〇〇の研究を行ない××の成果をあげることができた」「〇〇職に就きたかったため、△△の資格を取得することができた」など、アルバイトの時間を削ってどんなことをしていたのか書くようにしましょう。
短期アルバイトの場合は身につけたことをアピールする
学生によっては、長期間のアルバイトが勉強によって不可能な場合もあります。
しかし、「こんな短期アルバイトをやった」とだけ記載しても企業側は事情がわからず、「仕事が長続きしないのではないか」とマイナス印象にとられてしまうこともあります。
このような場合でも、短期間で身につけたことや、応募企業での仕事にどのような点で活かすことができるのかをきちんと書くようにしましょう。
複数アルバイトの掛け持ちはすべてを書く必要はない
アルバイトをいくつも掛け持ちしていた場合、様々なアルバイト経験がアピールになると思いがちですが、経験だけでは高評価にはつながりません。
また、複数アルバイトについて書くがあまり、一つ一つの内容が薄くなってしまったのでは意味がありません。
応募企業の仕事との関連性やアルバイト経験がどのように活かせるのか、アピールしたいことを明確にし、アルバイトは複数記載するのではなく、絞って書くようにしましょう。
まとめ
企業はエントリーシートを通じ、社会経験の有無や自社の社風とのマッチ、物事に取り組む姿勢などを知るためにアルバイト経験を質問しています。
アルバイト経験では具体的な社名や店名は記載せず、取り組んだ姿勢や気づいたこと、学んだことを書き、成果はできるだけ数字などを用いて具体的に表わしましょう。
また、アルバイト経験を通じ、応募企業の仕事にどう活かせるかを書くことが重要になります。